どうも、ほにゃらら sp.です。
今回のテーマは熱帯魚の寿命について。
熱帯魚は生き物である以上、当然寿命もあります。
そしてその寿命の長さは、種類によって全く異なります。
寿命は長ければ長い魚種ほど、その魚とは長い付き合いができます。
一方で寿命が長い魚種は将来飼い続けるための長期計画が重要になります。
寿命が10年を超えるような魚種は、ライフスタイルが変わっても飼い続けることができるのか、よく考えてから飼育しなければなりません。
そのためには、魚種ごとの寿命を知っておくことが重要です。
寿命が短い順に紹介していきます。
1年以内の魚
いわゆる年魚と呼ばれる魚種です。
誕生、成熟、繁殖のサイクルを1年の中で行い、次の世代へとつなげます。
このグループを観賞魚として楽しむ場合、繁殖を前提としているところがあります。
成魚の期間は短いものの、繁殖させることで毎年楽しめます。
卵生メダカの中でも、ノソブランキウス属の多くの魚種は年魚です。
このグループはアフリカ大陸の乾季に水が干上がってしまうエリアに生息しており、乾燥に耐えられる特殊な卵を産むことが知られています。
乾季の訪れにより水が干上がれば、当然親魚は死んでしまいます。
しかし乾燥に耐えられる特殊な卵は、次の雨季を待ち世代交代ができるのです。
累代をつなぐためには、少しでも成魚の期間を長く伸ばすことが重要です。
そのためには以下の2点を守ると良いでしょう。
- 脂肪分の多いエサを控えること
- やや低めの水温で管理すること(22~24度程度が理想的です。)
幼魚のうちからエサや温度管理をしてしまうと、健康的に成長できません。
成魚になってから調整するのがおすすめです。
上手にコントロールできれば、観賞期間を長く楽しめます。
▼こちらも参考
2~3年の魚
小型熱帯魚としてポピュラーな魚種の寿命は、おおよそ2~3年程度であることが多いです。
卵胎生メダカ類や群泳させるタイプの小型魚の多くは、ふつう3年程度で寿命を迎える種が多いです。
ベタや小型グラミー、ドワーフシクリッド(ラミレジィやアピストグラマなど)、ハゼといったスズキ目の小型魚も、通常3年程度が目安です。
こちらの魚種は飼育環境が格段に良いと、まれに3年以上生きることもあります。
レインボーフィッシュも概ね3年程度が目安です。
ブルーレインボーやハーフオレンジレインボーなどの中型種に関しては、5年程度生きることがあります。
4~9年の魚
いわゆる中型魚と呼ばれるグループと、ナマズ目の小型魚が主に属します。
ポピュラーな魚種の中でも、比較的寿命が長い部類に入ります。
ここで紹介している魚種は5年前後で寿命を迎え、10年には満たないことが多いです。
長い付き合いが楽しめますが、その一方で飼育にはある程度の長期計画が必要です。
コリドラスやプレコ、フライングフォックスは掃除要員としてもよく採用されますが、意外と寿命も長い魚種です。
主役となる小型魚より長生きすることも多く、環境が適切であれば4~5年程度は飼育を楽しめます。
10年以上の魚
10年以上生きる魚種は、観賞魚としては長寿と言えます。
いわゆる大型魚や古代魚と呼ばれる魚種が多く属します。
10年以上もの時を一緒に過ごす可能性があるのですから、飼育の際は相応の長期計画が必要です。
個体によっては、20年近く生きる場合もあります。
ほとんどの種は大型に成長します。
購入時のサイズは小さく、60cm以下の水槽での飼育が適することもありますが、最終的には大型水槽での飼育が必須となることがほとんどです。
これらの魚種は最終的に90cm以上の水槽を考慮に入れ、長期計画を立ててから購入してください。
なお大型魚は飼育方法により、サイズをある程度調節することが可能です。
大きくしたい場合はできるだけ単独でゆったり飼育し、給餌頻度と換水頻度を上げましょう。
たくさん食べさせてたくさん水換えすると、すくすくと大きくなります。
水温も高めに設定した方が、大きく育つ傾向があります。
逆に小さくしたい場合は過密気味に飼育し、給餌頻度を落とすと良いです。
毎日ではなく、2~3日に1回程度餌を与えると良いでしょう。
水温を低めに設定すると、成長が鈍化します。
とはいえ、大型熱帯魚なら25~26℃は最低でも欲しいところです。
エサ食いが極端に落ちたり、活性が悪くなってしまうようなら落とし過ぎです。
その場合は、水温設定を見直しましょう。
過密気味に飼育する以上、フィルターはろ過能力の高いものを使用しましょう。
また水も汚れがちになるので、換水頻度は多めが良いです。
このようにサイズを調節するテクニックを身につけておくと、ライフスタイルの変化にも合わせやすくなるかもしれません。
一方で、大型魚はやはり大きく育ててこそ魅力があります。
できるだけ安定した環境で大きく立派な個体へ仕上げ、飼育をお楽しみください。
主要な観賞魚のサイズと寿命
観賞魚を終生飼育するためには、最大でどのぐらいのサイズにまで成長するのかと、おおよその寿命を知っておくことが必要です。
各グループの代表的な魚種と、最大サイズ、おおよその寿命を一覧表にしました。
熱帯魚を飼育する際には、その魚とだいたい何年くらいの付き合いになるのか知っておきましょう。
長ければ長いほど長期間飼育を楽しめますが、一方でそれだけの期間、ライフスタイルの変化も加味して飼育計画を立てなければなりません。
| 魚種 | 最大サイズ(約) | おおよその寿命 | 備考 |
|---|---|---|---|
| グッピー | オス:3~4cm メス:4~6cm | 1~3年 | 繁殖力が強く、1ペアから100匹以上にまで増えることもあります。 |
| プラティ | オス:4~5cm メス:5~6cm | 1~3年 | 繁殖力が強く、1ペアから100匹以上にまで増えることもあります。 |
| ネオンテトラ | 4cm | 2~3年 | |
| ラスボラ・ヘテロモルファ | 4cm | 2~3年 | |
| アカヒレ | 4cm | 2~4年 | |
| ゼブラダニオ | 5cm | 2~5年 | |
| ラミレジィ (ドワーフシクリッド) | 6cm | 2~4年 | |
| アーリー (小型アフリカンシクリッド) | 15cm | 5~6年 | |
| フロントーサ (大型アフリカンシクリッド) | 35cm | 10~15年 | |
| エンゼルフィッシュ | 12cm | 5~7年 | |
| ディスカス | 18cm | 5~7年 | |
| ベタ | 7cm | 2~3年 | |
| ドワーフグラミー | 6cm | 2~3年 | |
| レインボー・スネークヘッド (小型スネークヘッド) | 15~30cm | 5~6年 | |
| レッド・スネークヘッド (大型スネークヘッド) | 80~130cm | 10~20年 | 大型種は1mを超えます。 |
| コリドラス | 6~10cm | 3~10年 | ほとんどは6cm前後です。 ロングノーズ種の一部で、10cm程度になる大型種もいます。 |
| タイガープレコ (小型プレコ) | 10~15cm | 5~6年 | |
| セルフィンプレコ (大型プレコ) | 30~50cm | 10~20年 | 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| レインボーフィッシュ | 5~8cm | 3~5年 | |
| アベニー・パファー (小型淡水フグ) | 3cm | 2~3年 | |
| テトラオドン・ファハカ (大型淡水フグ) | 40cm | 5~10年 | 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| シルバーアロワナ | 100cm | 10~15年 | 最大で1mを超えます。 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| アジアアロワナ | 100cm | 10~20年 | 最大で1mを超えます。 |
| ポリプテルス・セネガルス (上顎系ポリプテルス) | 30cm | 10~15年 | |
| ポリプテルス・エンドリケリー (下顎系ポリプテルス) | 70cm | 10~15年 | 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| ダトニオ | 60cm | 10~20年 | 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| オスカー | 30cm | 10~20年 | 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| フラワホーン | 30cm | 4~10年 | |
| レッドテール・キャット | 120cm | 15~20年 | 最大で1mを超えます。 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
| ピラルク | 200cm | 15~20年 | 最大で2mを超えます。 販売サイズは小さいことが多いので注意が必要です。 |
寿命を延ばすテクニック
観賞魚の寿命、観賞期間を延ばすテクニックは存在します。
以下のポイントを意識しながら飼育すると、平均寿命よりも長く飼育できるかもしれません。
- 成魚になったら脂肪分の少ないエサを与える
- 飼育水温を下げる
- 過度なストレスを与えない
- 本来の生体に合わせた環境を用意する
成魚になったら脂肪分の少ないエサを与える
自然下に比べ、水槽で飼育される魚は脂肪過多になりがちです。
成長が止まったら脂肪分の少ないエサや、植物質の多いエサに切り替えると長生きする傾向があります。
注意点として、成長期の魚にこれをやってしまうと小さいサイズのまま成長が止まり、逆に寿命が短くなることがあります。
十分に成熟してから切り替えるのが重要です。
飼育水温を下げる
飼育水温が高いと魚の活性が上がり、エサ食いも良くなり成長も早まります。
反面、老衰するのも早く、寿命が短くなってしまいます。
成魚になったらやや低めの水温で管理すると、観賞期間を長くできます。
多くの熱帯魚では、24℃程度が目安です。
それよりも下げるとエサ食いが極端に落ちたり、活性が悪くなることがあるので要注意です。
20℃を切ると、ほとんどの熱帯魚は調子を崩します。
こちらも注意点として、成長期の魚にはやらないほうが良いです。
また、水温を下げるとその分サイズも小さくなりがちです。
大きくしたい魚は、まず目標のサイズになるまでは高温で管理すると良いでしょう。
過度なストレスを与えない
ドアの開け閉めの振動や、極端な水温変化、強い水流などの極端なストレスは魚に取っても負担になります。
大きなストレスは与えないようにしましょう。
一方で、全くストレスフリーな環境よりも、適度なストレスがあった方が魚の運動量が増え、エサ食いも良くなる傾向があります。
例えば遊泳性の高い魚種なら水槽内に水流をつくったり、肉食魚なら活き餌を追いかけさせたりすると良いでしょう。
本来の生体に合わせた環境を用意する
ストレスと関連する部分となりますが、その魚種が持つ本来の習性に反する飼い方は、魚にストレスを与えます。
例えば群れる魚種なのに単独飼育したり、物陰に隠れる習性があるのに隠れ家が無かったり、砂に潜る習性があるのに底砂を敷かなかったり、というのはストレスがかかります。
できる限り落ち着いて暮らせるよう、その魚本来の生活環境を再現して飼育したほうが、結果的に状態良く飼育することにつながります。
その結果、寿命も観賞期間も長く楽しめるようになります。
熱帯魚の寿命 まとめ
▼こちらも参考



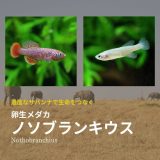






































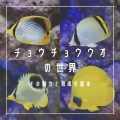

コメント